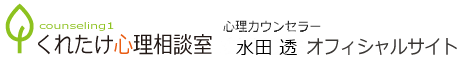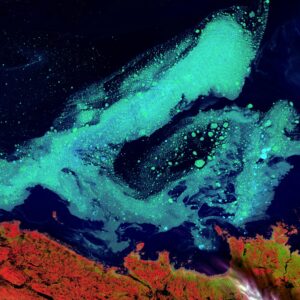門
カフカに『審判』という小説があります。
その最後のほうに、掟の門を守っている門番と、その門を通りたい一人の男の話が出てきます。
男は田舎からやって来て、掟の門のなかに入れてくれと門番に頼みます。けれども門番は、今は入ることを許すわけにはいかないと言う。
男は考えて、あとでなら入れてもらえるかと聞く。『あとでなら入れてやれるかもしれない。でも、いまはだめだ』と門番は言う。
掟の門の扉は開いてはいるし、門番は端の方に座ったので、男は門のなかを覗いてみようとする。
門番はそれを見ると笑って言う。『そんなに入りたいのなら、私の禁止に構わず入っていけばいい、しかし言っておくが、中にはさらにいくつもの門があり、私は下っ端の門番で、中にいる別の門番の力は次々と大きくなっていく。』
男はそれを聞いて、諦めて、仕方なく扉の脇に座って、何日も、何年も、扉に入れてくれる事を待ち続ける。
その間何もしなかったわけではない。門番にいろいろな方法で話しかけて、貢物なども渡した。
けれども門番はそれを受け取りはしたが、それは男に悔いが残らぬために受け取るだけだと言う。
男はいつしか掟の門ではなく、この門番が唯一の障害と思うようになる。はじめの数年間は、大声でこの不運な偶然を呪い、のちに男はだんだんと年老いて、余命少なくなっていく。そして最後に、男は門番に訊ねる。
『皆、掟を求めているのに、この長年の間、私の他に誰もこの門に入れてくれと言わなかったのは、どういう訳でしょうか?』
男には既に臨終が迫っていた。
門番はその耳に答えた。
『ここはおまえ以外の人間の入れるところではなかったのだ。なぜなら、この門は最初からただおまえだけのものと決められていたのだ。
さあ私も言って、門を閉めるとしよう。』
なんか最近ふと、まだ幼い頃に読んだこの話を思い出しました。カフカというのはだいたいこんな話ばかり書いているのですが、この話は『審判』の中に出てくる登場人物の話す逸話として出て来て、登場人物達はこのあとこの話の解釈を延々としています。
彼の物語は入れ子構造になっていて、箱の中の箱の中の箱、みたいな印象があって、小さな頃に読んだ時にそこが面白かったのです。勿論心理的な興味もあったのでしょう。
でもいま思い出した理由は、人間の意思や意識は、その語る(思考する)人自身と、それを聞く(見る)誰かのあいだにしか存在していなくて、それ以外の事はあまり気にしなくてもいいのかもしれないなという自分の気持ちと、このエピソードがリンクしているからかな、と思いました。

投稿者プロフィール

最新の記事
 カウンセリング2026年2月4日静かな生活
カウンセリング2026年2月4日静かな生活 カウンセリング2026年2月3日心理的安全性って実際どういう意味?
カウンセリング2026年2月3日心理的安全性って実際どういう意味? カウンセリング2026年2月2日大切にされることに身構える
カウンセリング2026年2月2日大切にされることに身構える カウンセリング2026年2月1日2月のカレンダーを更新いたしました
カウンセリング2026年2月1日2月のカレンダーを更新いたしました