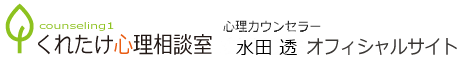何故学校に行くのか/何故仕事をするのか
くれたけ心理相談室の5月のブログテーマの一つ目は、
「あなたは何故、仕事をするのでしょう。何故、学校に行っていた(いる)のでしょう。」です。
まずは「なぜ、学校に行くのか」から考えてみたいと思います。
私は義務教育の頃、この問いについて考えたことがありました。
まだ若く、いろいろと悩んでいた時期です。
その後、さまざまな経験を通してひとつの気づきがありました。
それは「学ぶことは自由になること」だということです。
もちろん、学校という場が逆に自由を奪ってしまうこともあります。
特定の価値観を無意識に刷り込まれてしまうことは、とても残念なことです。
私は大学での学びも大切だと思っていますが、
本当は、すべての経験が「学び」だと思っています。
楽しいことを経験すれば、「楽しい」という感覚を知る。
嫌なことがあれば、それを経験した誰かの気持ちを想像できるようになる。
たとえば「一人っ子は自分のことしか考えない」と言われるのは、兄弟との関わりから得る学びを前提にしているからかもしれません。
そして何よりも、学びを「自分のもの」にするためには、「自己」が必要です。
自分という存在があってこそ、学びが意味を持ってくる。それが、私が学ぶことの意味について考えてきたことです。
次に、「なぜ、仕事をするのか」について。
実のところ、私にとって「仕事」とはなんなのか、今も時々考えます。
たとえば、小説家・野崎まどさんの『タイタン』という作品には、AIが発展し、人が働く必要がなくなった未来の世界が描かれています。
主人公はそこで、AIの人格に対して、カウンセリングというコミュニケーションの仕事を始めることになります。
この物語の中では、人々は「仕事」をもはや生活のためではなく、趣味のようなものとして認識しています。
また、もう一つ思い出すのは、村上春樹さんの仕事に対する考え方です。
彼にとって仕事とは、「自分」と「読者」とのあいだにあるもの。
彼は批評家の評価を気にしないし、それを良くないものと見ています。
昔、小説の世界には「文壇」という閉じたコミュニティがありました。その場所では彼の小説は「あんなものは小説ではない」という扱いでした。
けれども、彼はずっと読者との関係を大切にして、こつこつと作品を書き続けてきました。
そして今では、世界中に読者のいる作家になっています。
私はこの「自分」と「誰か」とのあいだにあるものこそ、仕事の本質のように思えるのです。
それは他者とのつながりの中で、自分が何を感じ、何を届けられるのかということ。相手が何を感じ、何を受け取ったと捉えられるか、そのあいだを丁寧に見ていくということ。
その為には、自分の感性や感覚はとても大事だと思います。
そこに、仕事をする理由があるのではないかと、私は考えています。
投稿者プロフィール

最新の記事
 思考2025年12月19日今日できる最高のこと
思考2025年12月19日今日できる最高のこと 未分類2025年12月18日音楽を聴くように
未分類2025年12月18日音楽を聴くように 思考2025年12月17日今日はちょっと整えられない日(もある)
思考2025年12月17日今日はちょっと整えられない日(もある) 未分類2025年12月16日あなたは羅針盤
未分類2025年12月16日あなたは羅針盤